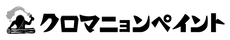DIY塗装の正しい順番や手順はご存じですか?
単純に木材に塗るだけ、と思われるかもしれませんが、下準備などの手順を踏むと、仕上がりがぐっと変わってきます。
今回は、正しい塗装の手順を徹底解説していきます!
目次
はじめに
道具は揃っていますか?
まずはじめに、塗装道具が揃っているか確認してみてください。
| 1. 下準備 | 2.塗装 | 3.後片付け |
|
|
|
ほとんど安価で揃えることができます。
塗装を始める前に、用意しておくといいですね。
組み立てと塗装、どちらが先か?
組み立てるのが先か、塗装をするのが先か、どちらがよいのか考えたことはありますか?
答えはズバリ、目的や優先順位によって変わってきます。
あなたが塗装したいものは、どちらが先がよいのでしょうか。以下の表を参考にしてみてください。
| 先に塗装 | 先に組み立て | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
塗装は乾燥に時間がかかり、塗装環境にも左右されがちです。
小物類を作るなら環境や組み立てを気にせずに作れます。
大きめの椅子などの塗装は、塗装を先に行うと組み立ての寸法が狂って使用時の危険性が高まります。一方で、組み立てを先に行うと塗装から乾燥までの間、保管場所に困ってしまいます。
接合部分だけ塗装を避けるなどの工夫をして、ご自身の塗装環境も考えてどちらを先にするか決めてから作業するようにしましょう。
1.仕上がりに一歩差をつける、2つの作業
塗装に入る前に、いくつかの工程を踏むことで仕上がりが大きく変わってきます。
- 研磨
- マスキング
1)研磨
まず1つ目が研磨です。やすりがけとも言います。
研磨をして木材に軽く傷をつけることで塗料が染み込みやすくなります。
また、もし木材に棘が残っていた場合にそのまま塗装をするのは大変危険ですので、やすりがけは必ず行うようにしましょう。
【具体的な研磨の方法】
紙やすりを使う方法が一般的です。手に入りやすく、100均やホームセンターでもかなり安価で売っていますのでぜひ探してみてください。
|
豆知識 紙やすりには番号がついていますが、番号が低いほど目が荒く、高いほど目が細かくなります。
#1000番以上のやすりもありますが、4桁以上になると金属向けのやすりになるため、木材の研磨ではあまり使われません。 逆に#80などの2桁のやすりは、主に木材に元々大きい傷がついていた場合や、別の塗装がついていた場合に剥がす目的で使用されます。 木材の横のケバケバ部分がひどい場合は、こちらで一気に除去するのもオススメです! |
広い面積部分はあて材を使うと均等な力で研磨できます!余っている端材で試してみてください。

|
豆知識 紙やすりを使うときに、ハサミを使って切っていませんか? 紙やすりは砥粒を貼り付けた紙なので、ハサミで切ってしまうとハサミの方が傷つき、切れ味が悪くなってしまいます。 折り曲げてある程度の跡をつけてから、手でちぎって使うのがオススメです。 |
よくある失敗
研磨作業のよくある失敗として、やすりがけをした後に木材についたままの粉が拭き取りきれていないことがあります。水を含ませ、十分に絞った布巾で拭き取ってから塗装に入りましょう。
2)マスキング
やすりがけができたら、マスキングをしましょう。
マスキングは塗りたくない部分にテープなどを貼り、塗料がはみ出すのを防ぐ作業です。
小物のDIYならマスキングテープで十分!作業のコツは、マスキングテープをしてから塗装をし、塗装が完全に乾く少し前に剥がしてください。完全に塗料が乾いてしまうと、塗料がテープと一緒に剥がれてしまう可能性があるので注意してください!
|
豆知識 応用編として、例えばアルファベットなどの文字の形にマスキングすることで、文字が浮き上がるような塗装が可能です。  |
2.いよいよ塗装へ!
下準備ができたら、いよいよ塗装に入っていきます。
今回は刷毛を使った塗装の方法をお教えします。刷毛を使わずにもっと簡単に塗装がしたい!という方には、刷毛が要らない塗料をこちらで紹介しておりますのでぜひチェックしてみてください。
塗装の手順
- 刷毛の毛を落とす
- 1度塗り
- やすりがけ
- 2度塗り
-
仕上げ
1度塗り
刷毛につける塗料の量ですが、一度に大量の塗料をつけると、乾くまで時間がかかってしまううえ、色むらもできやすくなります。
塗料が多くついてしまった時は、缶や新聞紙、汚れてもいいタオルなどで刷毛についた塗料を調節しましょう。
注意!
塗る前に、新品の刷毛を使う場合は揉むなどをして、すでに抜けている毛を落としてください。
※これを行わないと、塗っているときに木材に毛がつく可能性があります!
刷毛に塗料をつけたら、いよいよ木目に沿って塗っていきます。
塗った後に、「仕上がりの色味が薄い気がする…」と思った場合は、2度塗りをしてください。
2度塗り
2度塗りをする前に、1回目の塗装が完全に乾いてから再度軽くやすりがけをします。
#240ぐらいの紙やすりで軽くやすりがけをし、粉をしっかり取ってから2回目の塗装をしてください。
1回目と同じ量の塗料を刷毛につけて塗っていきましょう。
仕上げ
完全に乾いたら、必要な場合はニス塗りをして完成です。
どのくらい知っていますか?塗料の種類について
あなたが使っている塗料には、どんな特徴があるのかご存じでしょうか?
実は、仕上がりや用途によって、塗料の種類が異なります。
様々な塗料があるので下記の表を参考にしてみてください。
塗料にはさまざまな種類がありますが、大きく分けて水性と油性に分かれます。塗料は着色剤と樹脂、溶剤等で構成されています。水性か油性かどうかは、溶剤が水か油かの違いです。
| 油性塗料 | 水性塗料 | |
| 臭い | きつい | 少ない |
| 光沢 | 出やすい | 出にくい |
| 密着性 | 高い | 普通 |
| 後処理 | 硬化剤で固めて捨てる | 新聞紙などに染み込ませて可燃ゴミとして捨てる |
初心者にオススメなのは水性です。
臭いや後処理が楽になってくるため、あまり塗装のスペースが取れない方や、家の中で小物を作るという方にも水性をオススメします。
また、塗料の種類を調べると、「ステイン」「ワックス」など色々な名前が出てきますが、すべて水性のものと油性のものが存在します。
| ステイン | ワックス | ニス | |
| 特徴 |
|
|
|
どの塗料を使っても、油性は密着度はありますが臭いはきつい、といった特徴は変わりません。
ご自身の環境や目的に合わせて水性か油性かを選び、仕上がりのイメージに合わせて塗料の種類を選ぶと良いでしょう。
|
豆知識 塗料は多くの場合メタノール、シンナーなどの有害成分を含んでいます。 臭いによる不快感を軽減するため、クロマニョンペイントでは香料を配合した塗料を販売しております。 |
3.道具や塗料の保管方法
塗装が終わったら、換気を忘れずに行ってください。
道具や塗料は正しく片付けることで長持ちします。ここでは塗装刷毛の洗い方から保管方法までの流れと、塗料の保管方法をご説明します。
1)塗装刷毛の洗い方
実は刷毛にも正しい洗い方があります。
大量に塗料がついている場合は、まず新聞紙や汚れてもいい布で拭き取ります。
【水性塗料の場合】
水性塗料は水に溶けるため、そのまま水を貼ったバケツなどに浸けて洗いましょう。
【油性塗料の場合】
油性塗料の場合は、ペイントうすめ液またはラッカーうすめ液に浸けて洗ってください。
どちらもある程度綺麗になったら、食器用洗剤でもみ洗いするとさらに綺麗になります。
|
豆知識 「すぐに洗えない!」という状況の場合は、刷毛を塗料をつけたまま放置せず、水につけて置いておいておくことをオススメします。 そうすることで、水性塗料は水に溶け出し汚れが落ちやすくなります。油性塗料は落ちませんが、刷毛が塗料で固まってしまうのを防ぐことができます。 |
どちらも洗えたら、刷毛部分を上向きにして干します。
下向きにすると、もし洗い残しがあった際に塗料が刷毛の毛先の方で固まってしまう恐れがあるので必ず上向きにしましょう。

また、刷毛の手入れが大変という方には、クロマニョンペイントで開発している刷毛を使わない塗装方法をオススメします。
容器にスポンジが付いているハンディステインは、下準備さえ終わっていればすぐに塗る事ができ、保管や後片付けも楽になります。
布の端切れなどを使って塗れるカフェワックスとカラーペーストは、刷毛を使う必要がなく、使った布はそのまま破棄できるので手軽に扱えます。また、液状ではなく固めのテクスチャーで出来ているため、周りを汚しづらく設計されています。
よくある失敗
もし、刷毛が固まってしまった!という場合、水性塗料を使った刷毛は水にしばらくつけることで復活します。
油性塗料を使った場合はラッカーうすめ液につけることで復活しますのでお試しください。アクリルのうすめ液もありますが溶解力が弱いため、ラッカーうすめ液を使うと良いでしょう。
2)余った塗料の保管方法
塗料を保管する場合
余った塗料があった場合の保管方法をご紹介します。
- しっかりと蓋を閉める
- 蓋に隙間がないか確認する
- 残りの塗料が少ない場合は他の小さい容器に移す
- 火や水場の近く、直射日光の当たる場所を避け冷暗所に保管
基本的に塗料は、空気に触れることで固まります。
容器に空気が入らないようにすること、容器内になるべく空気を残さないように容器を変えるなどの工夫が大切です。
塗料を捨てる場合
塗料を捨てる場合は、新聞紙などに広げて、乾燥させてからゴミ箱へ捨てます。
量が多い場合は硬化剤を使い、固めてから捨ててください。
|
豆知識
自治体に出す方法もありますが、場所によっては出せない地域もあります。 |
注意!あなたはやっていませんか?
余った塗料は、河川や海などには流さないでください。
水性塗料は水に溶けるため外に流してもいいと思われるかもしれませんが、塗料には有害物質が含まれるため、水質汚染の原因になります。
そのため、なるべくシンクや排水溝にも流さず、新聞紙などに染み込ませて乾燥させた後に処分する方法が良いでしょう。
そもそも塗料の処理が面倒だ!という方は、使い切りしやすい容量の塗料を購入することをお勧めします。
クロマニョンペイントは手に取りやすい容量と価格で塗料を販売しています。ぜひ手に取ってみてください。
4.まとめ
塗装の過程は非常にシンプルで、初心者の方でもお気軽に試せることがわかりましたね!下準備や、どの塗料をどう塗るか、どれくらい丁寧に行うかで仕上がりが大きく変わってきますので、色々試しながらDIYを楽しんでください!
また、作品の参考例として、Instagramのハッシュタグ「#100均DIY」「#簡単DIY」や、小物DIYの特集ページを参考にしてみると良いかもしれません。